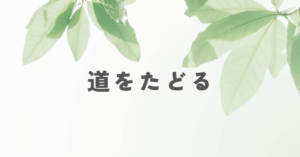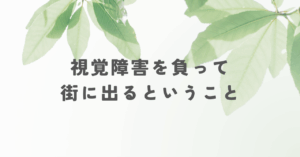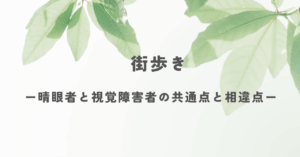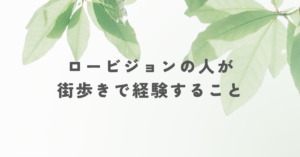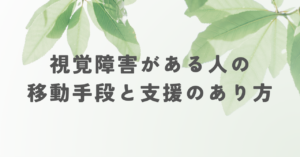多様化する移動手段
日常生活を送るうえで、移動は欠かせない要素です。
通勤・通学といった定期的な移動に加え、買い物や余暇などの不定期な移動も日常的に求められます。
人はこうした移動に際して、さまざまな手段を使い分けています。
パーソナルな移動手段としては徒歩、自転車、自動車などがあり、公共的な手段としてはバスや電車が挙げられます。
タクシーはその中間的な存在と言えるでしょう。
近年では、スクーターや電動車いすもパーソナルな移動手段として普及しており、
電動アシスト機能の進化によって、その機動力も向上しています。
さらに、カーシェアリングのような仕組みも都市部を中心に広まり、移動手段の選択肢はより多様化しています。
便利な自家用車
また、就労年齢層における運転免許保有率は約9割、自家用車の保有率も8割近くに達しており、
自家用車は主要な移動手段となっています。
自家用車には、ドア・トゥ・ドアで移動できる利便性、天候に左右されにくい点、大量の荷物を運べること、
必要なときにすぐ出発できる点など、多くの利点があります。
特に、公共交通機関の運行が限られる地域では、その利便性が際立ちます。
視覚障害と運転免許
しかし、誰もが自動車を運転できるわけではありません。
視覚障害のある人はその典型的な例です。
障害の程度にもよりますが、多くの視覚障害のある人にとって運転免許の取得は困難であり、
中途で視覚障害を負った場合には、それまで保有していた免許を返納せざるを得ないこともあります。
「パーソナルな」移動手段
視覚障害のある人にとっては、徒歩を除くほとんどのパーソナルな移動手段を自ら操作することが困難です。
そのため、実質的に利用可能なパーソナルな移動手段は「徒歩」に限られる場合が多くなります。
徒歩にも、道具を使用しない方法のほか、白杖や盲導犬を使用する方法、
さらに同行援護従事者の支援を受ける方法などがあります。
ただし、同行援護には第三者の介在が伴うため、厳密には「パーソナルな」移動手段とは言いがたいかもしれません。
まとめ
移動手段の多様化が進む現代においても、すべての人が同じように自由に移動できるわけではありません。
特に視覚障害のある人にとっては、自動車や自転車などの移動手段を利用することが難しく、
移動手段の選択肢が限られる現状があります。
これを踏まえると、移動の自由をより多くの人が享受できる社会を実現するためには、
公共交通機関のバリアフリー化や、支援技術の発展、社会全体の理解と協力が欠かせません。
今後さらに誰もが移動しやすい環境づくりが求められるでしょう。