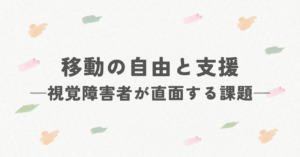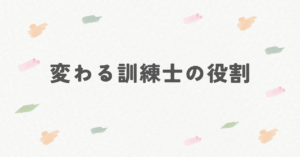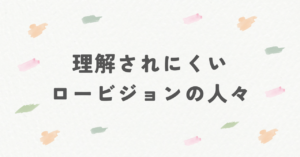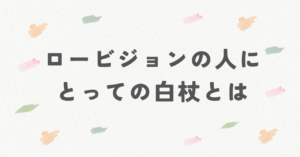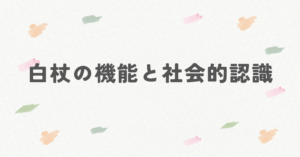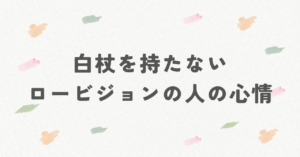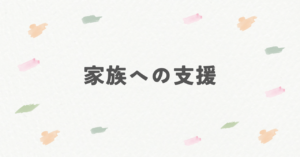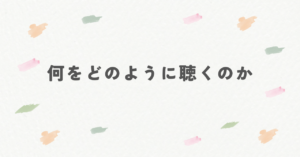「障害」の3つの階層
長い間、「障害」という言葉は漠然と捉えられていました。
しかし、1980年にWHO(世界保健機関)が「国際障害分類」を発表し、障害を以下の3つに分類しました (文献1)。
インペアメント(Impairment) – 身体的または機能的な損傷
ディザビリティ(Disability) – インペアメントによる能力の制限
ハンディキャップ(Handicap) – 社会的な不利
この定義によって、「障害」という言葉が持つ曖昧さが払拭され、社会の人々の理解が進んだと考えられます。
従来は一括りにされていた「障害」という概念が、
身体的な状態(インペアメント)、
その結果生じる能力の制限(ディザビリティ)、
さらに社会的に生じる不利益(ハンディキャップ)へと整理され、明確になったのです。
障害者グループが提示した新たな視点
一方、1970年代の英国では、
急進的な障害者グループ 「身体障害者隔離反対連合(UPIAS, Union of Physically Impaired Against Segregation)」 が、
新たな視点を提示しました。
彼らは、「障害者は抑圧されたグループであり、社会のバリアが彼らの生き方を制限している」と定義し、
社会そのものが障害を生み出していると主張しました(文献2)。
UPIASの目的は、隔離施設の廃止、障害者の社会参加の実現、独立した生活の確立、自己の人生をコントロールできる環境の構築でした。
「社会モデル」の基盤
UPIASの考え方では、障害を「インペアメント」と「ディザビリティ」に分け、
ディザビリティを社会が引き起こす不利益や活動制限として捉えました。
これが後の「社会モデル」の基盤となりました。
一方、WHOの定義は「医療モデル」と呼ばれ、
障害を個人の問題とし、医療やリハビリテーションによる改善を重視する考え方です。
続きは↓
参考文献
1. World Health Organization. International classification of impairments, disabilities and handicaps. 1980.
2. Shakespeare, Tom (1997). The social model of disability. In Lennard J. Davis (ed.) The Disability Studies Reader. Psychology Press.