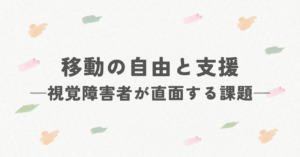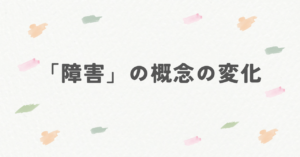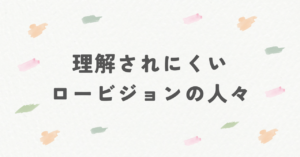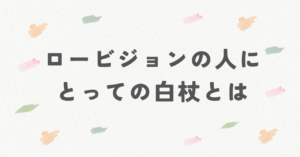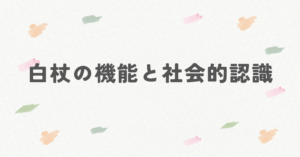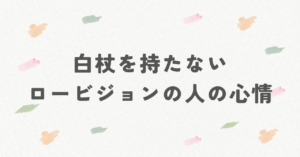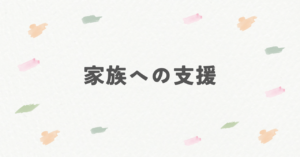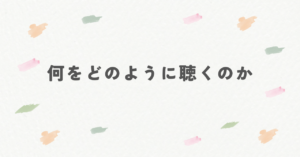医療モデル
「医療モデル」では、ディザビリティ(Disability)の原因はインペアメント(Impairment)にあると考えます。
例えば、視機能の低下によって
「物が見えない」「周囲のものとの位置関係がわからない」といったディザビリティが生じます。
このディザビリティを補うために、補助具(単眼鏡、ロングケインなど)の使用や、
操作技術の習得が推奨され、個人の適応努力が求められます。
障害のある人は、それぞれのディザビリティに対処するために工夫し、最善の努力をすることを期待されてきたのです。
社会モデル
一方、「社会モデル」では、ディザビリティの原因は社会の構造や制度にあると考えます。
障害のある人が社会的な活動を行う際に生じる困難や不利益が問題であり、
これにはWHOの定義における「ハンディキャップ(Handicap)」が含まれます。
視覚障害のある人の場合、「見えないからできないこと」は、社会的要因によって生じているため、
その社会的要因を改善すべきと主張します。
例えば、安全に移動するためには点字ブロック、音響信号機、同行援護サービスなどの整備が求められます。
本当の意味での「自立」とは?
長年、OM訓練では「ひとり歩き」が望ましい目標とされてきました。
そのために、視覚障害のある人はロングケインや盲導犬を使って歩く技能の習得に努めてきました。
人と一緒に歩く場合でも、視覚障害のある人自身が主導権を持っていれば、それは「ひとり歩き」の一形態と認められていた。
しかし、ある時、日常的にひとり歩きをしない全盲の人が、ひとりで米国まで渡航した事例がありました。
普段、自宅周辺の外出ですら人の手を借りていた人が、どうやって米国まで渡航し、目的地へ到達したのでしょうか。
驚いて尋ねると、その方法はシンプルでした。
タクシー、鉄道、航空機などの公共交通機関を利用し、各場面で関わる人々の支援を受けながら移動したのです。
この事例は、従来の「ひとり歩き」の概念に疑問を投げかけています。
果たして、ロングケインや盲導犬を使って歩くことだけが「自立」なのでしょうか?
むしろ、移動の目的を達成するために社会のリソースを適切に活用する能力こそが、
本当の意味での「自立」ではないでしょうか。
変わる訓練士の役割
現在、視覚障害のある人が安全な移動環境を求め、鉄道駅のホーム、踏切、交差点などの問題点を指摘し、
改善を強く要求する動きが活発になっています。
従来の「伝統的なOM訓練」(文献)は、環境を所与のものとし、
視覚障害のある人が個人の努力で適応することを前提としていました。
しかし、社会モデルの視点では、環境そのものが変わるべきだと考えます。
伝統的なOM訓練では、訓練士の役割は「視覚障害のある人が環境に適応できるように指導すること」でした。
例えば、視覚障害のある人が信号機の色を確認できない場合、車両音を頼りに信号の状態を推測する技術を習得させます。
しかし、社会モデルの視点に立つと、
「そもそも視覚障害のある人が安全に信号を確認できる仕組みを作るべきではないか?」
という問いが生まれます。
このように、社会モデルの理念に沿った専門家の役割は、従来の「専門家主導で指導する存在」とは異なります。
求められるのは、一方的に指示・指導する訓練士ではなく、
視覚障害のある人と共に課題を考え、解決策を模索するパートナーと言えるでしょう。
参考文献
Hill, P. & Ponder, P. (1976). Orientation and mobility techniques, a guide for the practitioner, American Foundation for the Blind, New York.