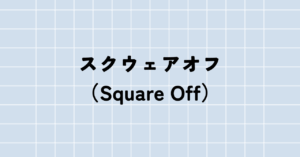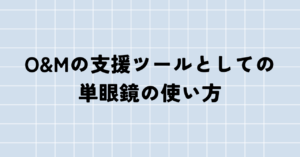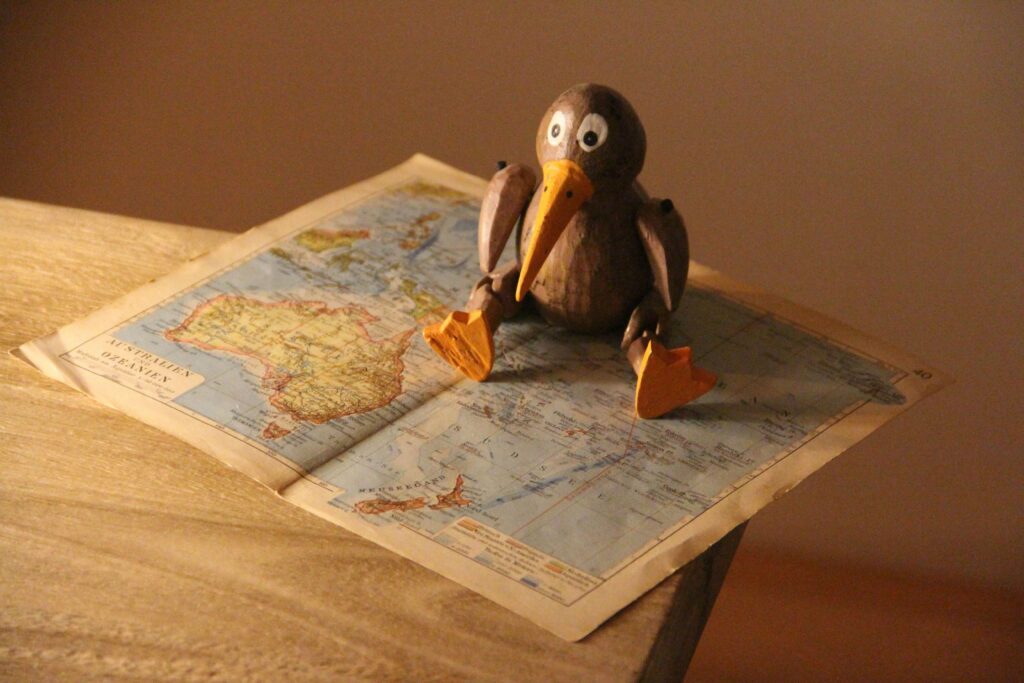
空間の分類とナビゲーションの基本概念
視覚障害者にとって、空間の理解と安全な移動は日常生活における重要な課題です。
空間情報の獲得方法は,対象となる空間スケールによって異なります。
Montello(1999)は、地理空間を以下の二つに分類しています。
・眺望的(vista) 空間:移動しなくても視覚的に全体を把握できる範囲。
・環境的(environmental) 空間:移動しなければ全体を把握できない範囲。
晴眼者(視覚に障害がない人)は「眺望的空間」を視覚的に把握できますが、
視覚障害者は実際に移動しながら眺望的空間を認知しなければいけません。
一方、Petrie(1995)は地理空間を「近接環境」と「遠隔環境」に分けました。
このPetrieの「近接環境」は、Montelloの「眺望空間」と実質的には重なると考えられます。
この分類に基づき空間における移動行動は2種類に大別されます。
・ミクロナビゲーション
近接環境において、歩行面や障害物、道の境界線などを感知しながら、安全に中間地点へ移動する行動。
・マクロナビゲーション
遠隔環境にある目的地を目指し、進路選択や方向転換など高次の空間判断を行う行動。
ミクロナビゲーションの方法と課題
視覚障害者にとって、ミクロナビゲーションは安全で確実な移動のために欠かせない技能です。
主な手法には以下の3つがあり、それぞれの課題があります。
(1) 道を辿る
歩道や縁石、誘導用ブロック、ラインテープなど、「線状の手がかり」を頼りに移動する方法。
ただし、これらが不連続であったり、途中に障害物があったりする場合には、進路が逸脱するリスクがある。
(2) パイロッティング
ランドマーク、ビーコン、GPSなどを用いて自分や目的地の位置を特定する方法。
初めて訪れる環境では、ランドマークの位置情報を事前に取得する必要がある。
(3) 経路統合
歩数や方向の変化をもとに現在地を推定する方法。
筋肉や関節の感覚(固有感覚)や音の流れや風向きなども利用するが、精度には限界があり、
歩道からの逸脱や方向ミスが生じやすい。
文献
Montello, D. R. (1999). Thinking of scale: The scale of thought. Montello, D.R. & Golledge, R.G. (Eds.), Scale and Detail in the Cognition of Geographic Information, NCGIA Varenius Report, 11–12.
Petrie, H.(1995). User requirements for a GPS-based travel aid for blind people. In Proceedings of the Conference on Orientation and Navigation Systems for Blind Persons, (ed. J.M. Gill and H. Petrie), Hatfield, UK. 1-2 February. London: Royal National Institute for the Blind.

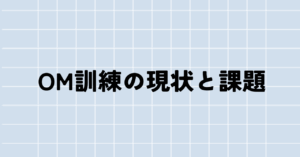
-300x157.png)
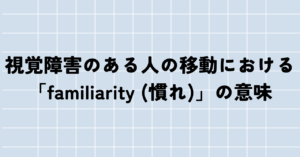
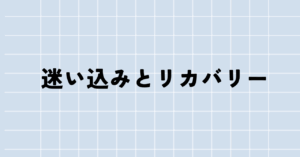
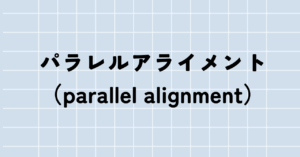
の使用場面と有効性-300x157.png)