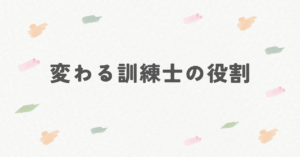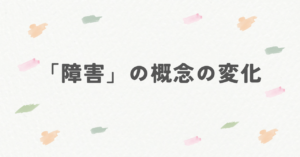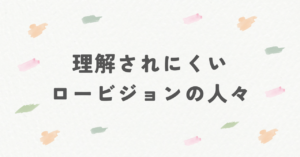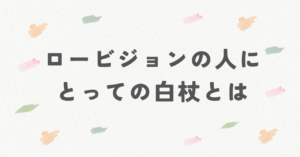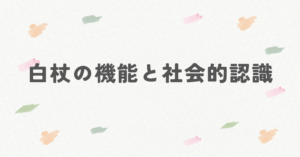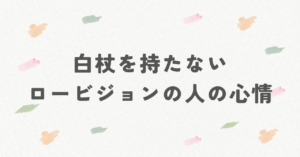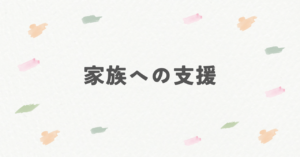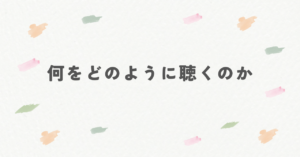公共交通機関の利点と課題
公共交通機関には、費用が比較的安価であること、運行スケジュールが決まっていること、社会の一員としての実感を得やすいことなどの利点があります。
一方で、駅やバス停といった特定の場所まで行く必要があること、悪天候やラッシュ時の混雑、ホームの危険、立ちっぱなしや荷物の持ち運びといった身体的負担、さらには自家用車と比べて移動時間がかかるといった課題も存在します。
移動に伴うコミュニケーション
視覚障害のある人が公共交通機関を利用する際には、駅員、バスやタクシーの運転手、乗客、通行人、商店主など、さまざまな人とのコミュニケーションが必要となります。
特に初めての場所では、駅構内や路上、電車内などで、道を尋ねる、現在地を確認する、信号の色を教えてもらう、ガイドを依頼するなど、多様な場面でのやり取りが求められます。
同行援護サービスを利用しているときは、常に同行援護従事者とのやり取りをしながらの移動となります。
「待ち時間」の負担
公共交通機関を利用する際の「待ち時間」も、視覚障害のある人にとっては一層の負担となることがあります。
乗り換え時の待ち合わせ時間は誰にとっても必要なものですが、視覚障害がある人の場合、同行援護従事者との待ち合わせや、駅員による案内を待つ時間などが加わり、晴眼者に比べて「待つ」時間が長くなる傾向にあります。
視覚障害者にとっての「移動」と社会的つながり
このように、視覚障害のある人にとって「移動」とは、単に目的地へ向かう手段であるだけでなく、他者との関わりや社会とのつながりを伴う営みでもあります。
そこには、自由度の制約や、他者の都合に合わせる必要、プライベートな場面に第三者が介在すること、望まない申し出を断らなければならない場面、あるいは支援を求めても応じてもらえないことなど、フラストレーションが蓄積しやすい状況が存在しています。