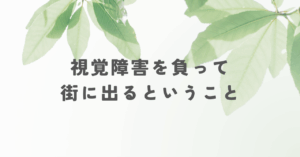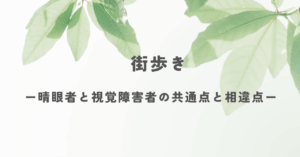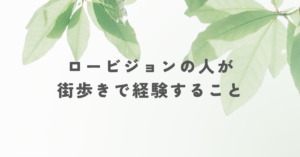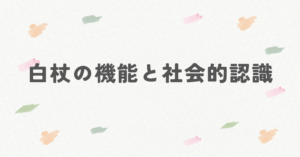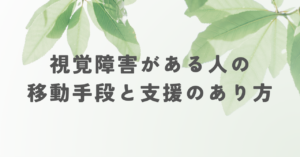歩道の両側にある境界
街歩きでは、「道なりに進む」という表現があるように、道路や歩道に沿って進むことは
ナビゲーションの基本的な方法の一つです。
前方を見通すことができない視覚障害のある人は、道路の方向を示していると思われるものを手がかりにして
進むことになります。
とくに重要なのは、歩道の両側にある境界です。
一つは民地との境界、もう一つは車道との境界であり、この二つが進行方向を判断するための大切な基準になります。
民地側の境界としては、壁、塀、生垣、側溝、異なる舗装面が接する境界 (ショアライン) などがあり、
車道側の境界には、ガードレール、植栽、並木、縁石などが含まれます。
一般的には、壁やガードレールのように高さのある構造物のほうが、視覚的、触覚的に認識しやすく、たどりやすいといえます。
「伝い歩き」「ショアライニング」
これらの手がかりは、視覚、手足の触覚、あるいは杖を使ってたどることができます。
しかし、それらは場所によって形状や素材が大きく異なり、出入口などでは途切れることもあるため、
使用者は変化に対応しながら、途切れた部分で進路を失わないように進む必要があります。
オリエンテーションとモビリティ(orientation and mobility) 訓練では、
こうした要素を「進路方向を示すもの(direction indicator)」や
「ある地点へ導く線 (guideline)」と呼びます。
そして、こうした構造物に沿って歩くことを「伝い歩き (trailing) 」、
舗装面の縁に沿って歩く場合は「ショアライニング (shorelining) 」と呼んでいます。

写真1
写真1では、民地側には背の高い生垣が、車道側にはガードレールが続いています。
両側に明確な境界があるため、視覚障害のある人にとっては比較的進行方向を把握しやすい歩道といえます。
歩道上には障害物もなく、伝い歩きに適した構造です。

写真2
写真2では、民地側にはブロック塀、車道側には植え込みと街路樹が続いていて、
こちらも比較的明確な境界が形成されています。
歩道上には物が一切なく、境界に沿って安全に歩くことができる環境です。

写真3
写真3では、車道側に駐輪スペースがあり、民地側にも自転車が多数停められています。
さらに、中央には視覚障害者用誘導ブロック(点字ブロック)が敷設されていますが、
自転車のハンドルなどが点字ブロックに干渉していて、伝い歩きが困難な状況です。
視覚障害のある人にとっては、安全な進行方向を維持するのが難しい歩道と言えるでしょう。
視覚障害者が歩道を歩くときに直面する困難
晴眼者にとっては、道そのものが進路を示すものであり、それを視覚的にたどることにほとんど困難はありません。
歩道の上に障害物があっても、多くの場合それらは歩道の両端に置かれています。
そして中央部分は空いていて通行可能です。
人が歩く空間は歩道の中央部分とみなされていて、その部分は確保されている一方で、
道の端には電柱のような固定構築物をはじめ、駐輪自転車や商店の陳列台などが存在するのが一般的です。
そのため、視覚障害のある人が道の方向の手がかりを歩道の両端に求めようとすると、
障害物に頻繁に接触し、それを回避する動作をくり返すことになり、進路方向を認識することが難しくなります。
しっかりとした方向の認識がないと、車道や空き地に気づかず入り込んでしまうといった事象が起こりやすくなります。
点字ブロックの必要性
視覚障害のある人が、点字ブロックを必要とする理由の一つのは、
それが進行方向を明確に示してくれる「確実な手がかり」になるからです。
視力が残っているロービジョンの人にとっても、視認性の高い点字ブロックは、
目で進行方向を追うための有効な手段となります。
言い換えれば、歩道の端を安全にたどることができない状況が、点字ブロックの必要性を高めていると考えられます。
例えば、写真1や写真2のように、両側に明確な境界があり、歩道上に障害物がない場合は、
点字ブロックの必要性は比較的低くなるかもしれません。
”Who put that there?”
イギリスの視覚障害者支援団体RNIBは、かつて ”Who put that there?” というキャンペーンを行っていました。
これは、違法な看板や放置自転車などが視覚障害のある人の歩行を妨げる障害物となっているとして、
それらを撤去し、安全な歩行環境を整えることを目的としたものでした。
混雑する歩行空間
歩道空間は、多様なモビリティニーズを持つ人々が共有する場所です。
たとえば、段差をなくしたい車椅子利用者と、段差を手がかりとする視覚障害のある人たちとの間には、
しばしば利害の対立が生じます。
さらに、高齢者に代表される移動弱者の増加、自転車や電動キックボードといった高速移動手段の混在が加わることで、
歩道の空間はさらに混雑し、誰にとっても安心に移動しづらい状況になっているのが現状です。
文献
RNIB(2015). Who put that there, https://media.rnib.org.uk/documents/Who_put_that_there_Report_February_2015.pdf