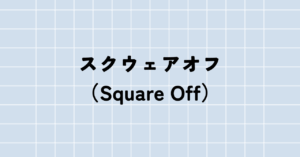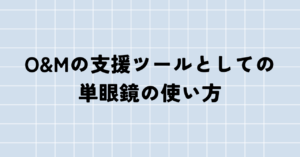環境への慣れがもたらす移動の容易さ
視覚障害のある人の移動の容易さを考えるうえで、「環境への慣れ(familiarity)」は重要な要素です。
たとえば、ある道を初めて歩く場合と、何度も通ったことのある道を歩く場合とでは、
得られる情報の量や質が大きく異なります。
新しい通勤路で、初めて駅に向かうときには、地図を見たり、人に道を尋ねたりして到着するかもしれません。
しかし、数日後には迷わずにたどり着けるようになり、
数か月も経てば、会話に集中していても自然に駅に到着できるようになるでしょう。
このように、日々の繰り返しによってルートは身体的に記憶され、
やがて意識せずとも移動できる状態が形成されます。
一度環境に慣れると、その場所への注意 (attention) は次第に薄れます。
新たな情報を意識的に取得しようとしない限り、その場所に関する知識の幅はあまり広がりません。
このような「慣れ」は、環境に対する注意の負担を軽減し、ストレスの少ない移動の達成に寄与します(大倉、1989)。
初めての環境で求められる情報収集と判断
一般に、初めて訪れる場所では、事前に得た情報(地図や説明など)に加え、
その場での情報収集が不可欠です。
歩行中は、環境から得られる情報を絶えず処理しながら、進行方向や安全性について判断を下す必要があります。
ここで大きな役割を果たすのが視覚です。
視覚による情報収集は、他の感覚に比べてはるかに効率的であり、
周囲の状況を一望し、短時間で必要な情報を把握することができます。
しかし、視覚障害があると、視覚による情報取得が制限されるため、
晴眼者が一目で得られる情報を収集するには、実際にその場所まで移動し、情報を収集しなければなりません。
つまり、情報を得るための移動自体も、「目的地へ向かうための移動」の一部として位置付けられるのです。
視覚障害のある人は、視覚の代替として、さまざまな手段を用いて情報を収集します。
たとえば、聴覚、触覚、固有感覚などの感覚を活用したり、
単眼鏡、カメラといった支援機器を使用したりします。
また、通行人に尋ねるといった方法もとられます。
これらの手段は、それぞれの状況に応じて柔軟に組み合わされます。
未知の環境に対する三つの学習ストラテジー
未知の環境に対して人がとる学習ストラテジーには、以下の三つのタイプがあります (Golledge, 1999)。
・試行錯誤的な探索:自身の感覚や経験則に基づき、自由に探索する方法。例:迷路を直感的に進むような方法。
・事前の情報に基づく計画的移動:地図や説明書などの情報源を参照して計画を立てる。
・訓練に基づく制御された探索: O&M指導で用いられる技術(境界に沿って歩く、経路統合、順序だった範囲探索など)に基づく探索。
Familiarizationというプロセス
O&M指導において、未知の場所を慣れた場所へと変えるプロセスは
「familiarization(環境への慣れの獲得)」と呼ばれています。
これは、
体系的な戦略を使用してランドマークを特定し、その他の場所や環境の特徴と関連づけながら、部屋や建物などの空間構造を学習していく組織的なプロセス
であると定義されています(Fazzi & Barlow, 2017)。
訓練士は、学習者が将来、自ら環境を理解し、適応できるようになることを目指して、このプロセスの習得を支援します。
familiarizationが特に重要になるのは、新しい地域に引っ越してきた直後のように、
生活に必要なルートの開拓が求められる場面です。
ルート学習では、出発点と目的地を結ぶ道順、曲がる方向、その順序などを正確に把握することが重視されます。
このときの主な関心は、ルートの構造や通過に必要な行動(たとえば「境界に沿って歩く」)を理解することであり、
ルート外の環境全体を詳細に把握することは目的ではありません。
ランドマークなどの環境的手がかりは、あくまで方向転換や区間の判断を補助するために認識されるにすぎません。
Familiarityという概念の二面性
「familiarity」という語は、Oxford辞典によると、
「誰かあるいは何かをよく知っている (know well) 状態」と
「見知っている (recognize) 状態」の両方の意味を持ちます。
前者は知識や経験、時間の積み重ねによって獲得された深い理解を指し、
O&M指導において目指されるfamiliarityはこちらにあたります。
一方、後者は「見たことがある」「知っている気がする」といった表層的な知識にとどまります。
たとえば、毎日通勤途中にすれ違うものの名前も知らない「見慣れた他人(familiar stranger)」のような存在は、
この表面的なfamiliarityの一例です。
無意識的な学習の積み重ね
このように、「familiarity」という概念は、深い理解と表層的な印象の両面を含むため、
曖昧で、とらえどころのない性質を備えています。
たとえば、いつも通っている通勤路で、工事のために迂回した際、
「こんな近くに、こんな店があったのか」と驚くような経験は、
環境に対する意識がいかに限定的であるかを示しています。
familiarityは、完成された知識の状態としてではなく、
時間をかけて形成される動的なプロセスと捉えるべきです(Felder, 2021)。
同じルートを何度も繰り返し歩くうちに、その空間は「当たり前」となり、
注意を払う必要のないものへと変化していきます。
これがfamiliarizationの本質であり、円滑な移動のための「ちょうどよい環境への慣れ」が成立する背景には、
こうした無意識的な学習の積み重ねがあるのです。
参考文献
大倉元宏(1989).二次課題法による盲歩行者のメンタルワークロードに関する研究,人間工学, 25巻4号.
Golledge, R.G. (1999). Human wayfinding and cognitive maps. In R.G. Golledge (Ed.), Wayfinding Behavior: Cognitive Mapping and Other Spatial Processes (pp. 5-45). The Johns Hopkins University Press.
Fazzi, D.L. & Barlow, J.M. (2017). Orientation and Mobility Techniques: A Guide for the Practitioner (2nd ed.), AFB Press.
Hornby, A.S. (2000). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (6th ed.). Oxford University Press.
Felder, M. (2021). Familiarity as a practical sense of place, Sociological Theory, 39(3), 180-199.

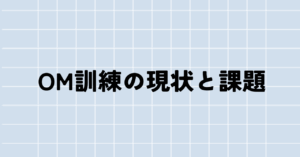
-300x157.png)
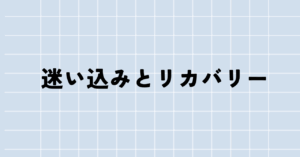
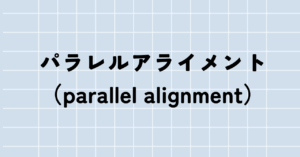
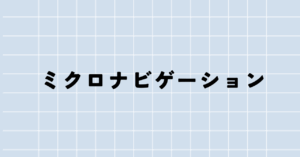
の使用場面と有効性-300x157.png)