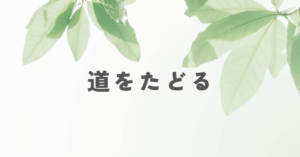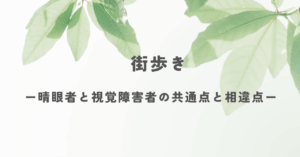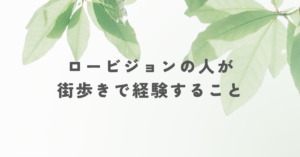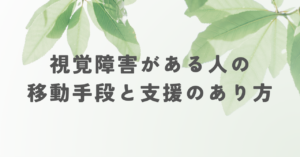「はじめてのおつかい」
「はじめてのおつかい」というテレビ番組がある。
幼い子どもが、人生で初めて一人でお使いに出かける様子を追ったドキュメンタリーである。
親はどのような思いで見守るのか、街の人々はどのように接するのか、店員は子どもとどのようにやりとりするのか。
そうした視点が交錯しながら、小さな冒険が展開される。
人気の高いこの番組は、子どもの成長の一場面を社会全体で見守るという構図を持っている。
番組の中で、子どもはさまざまな課題に直面する。
道順を間違えずに進めるか、信号を正しく渡れるか、自動車との危険な接触はないか、
目的地で用件を正確に伝えられるか。
制作スタッフが常に近くで見守り、危険な状況には即座に対応できる態勢があるとはいえ、
途中で起こるちょっとしたハプニングや子どもの戸惑いが、視聴者の心を惹きつける。
そして何より、それを乗り越えて帰ってくる姿に、多くの人が子どもの成長を実感し、喜びを共有する。
初めての社会的挑戦
このような「初めての社会的挑戦」は、人生の途中で視覚障害を負った成人にも、ある意味で共通する体験である。
社会人として長く生きてきた人が、ある日突然、視覚を失い、もう一度社会の中に出ていく。
それは、すでに経験した「社会との関わり方」を、まったく新しい方法で再構築する作業である。
たとえば、トーマス・キャロルのモデルでは、「見えていた自分」はある意味で“死”を迎え、
「見えない自分」として新たに誕生するとされる。
その立場に立てば、新たに生まれた“見えない自分”が、あらためて社会にデビューするプロセスと捉えることができる。
他方、そうした立場を取らず、視覚障害を負っても自分は変わらないと考える人もいるだろう。
しかし、たとえ「自分は自分のまま」と思っていても、見え方が変わり、歩き方が変わり、
それに応じて周囲の人々の態度も変化する。
つまり、本人の意識とは無関係に、社会の中での立ち位置は確実に変わる。
現実の生活空間での見え方
新たな視覚状態で再び街を歩こうとする時、記憶の中の街並みは今もそのままなのか、
自分の現在の視力では何が見え、何が見えないのか、
目的地まで無事にたどり着けるのか、段差や障害物を避けられるのか、信号を渡ることができるのか。
こうした問いに対する答えは、実際に街を歩いて確かめてみるほかない。
眼科の検査では“見え方”の数値は示されるが、
それが現実の生活空間においてどのような意味を持つのかは、実地で経験しなければわからない。
さらに重要なのが、「他者のまなざし」である。
視覚障害を負った自分を、街の人々はどう見るのか、どのように扱うのか、あるいは無視するのか。
それに対して、自分はどのような感情を抱くのか。
こうしたことも、実際に外に出て、他者と出会う中でしかわからない。
事例:聴覚と視覚の両方に障害を負った人の初めての一人暮らし
ある事例を紹介したい。
聴覚と視覚の両方に障害を負った人が、初めての一人暮らしを始めた。
アパートから徒歩15分、約1km離れた場所まで一人で移動する方法を検討したが、
その途中には6か所の道路横断があった。
そのうち1か所は上下4車線の国道で、残りは1~2車線の比較的狭い道路だった。
国道の横断については、近くの店舗の人の支援をお願いすることになったが、
他の5か所は通行人の助けを借りる必要があった。

(イメージ)
実際に通行人に援助を求めながら移動を試みたところ、市街地で人通りはあるものの、
横断ごとに協力者を見つけるまでに平均して5分ほどを要した。
横断にかかる待ち時間だけで約25分、歩行時間を合わせると所要時間はほぼ1時間に達した。
通行人の注意を引く工夫や声のかけ方などを試行錯誤したが、大幅な時間短縮にはつながらなかった。
最終的に彼が選んだのは、同行援護サービスを使って移動する方法だった。
これは単なる移動手段の選択の話ではない。
再び社会の中で、自分の力で動き、自分の意思で行動しようとした一つの挑戦の例である。
そしてその挑戦のプロセスにこそ、視覚障害を負った人がもう一度「社会に出ていく」ことの重みと意味がある。