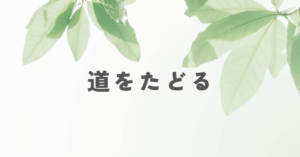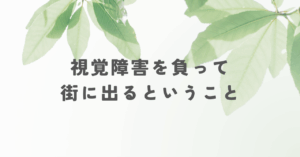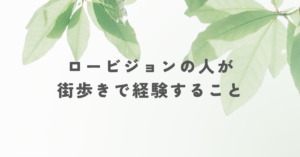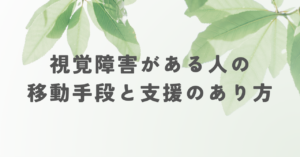風景が見えない時の移動
暗闇や濃霧のように周囲の風景が見えない状況で、人はどのように移動するでしょうか。
たとえば、「この方向へ何メートル進めば着くはず」と予測しながら歩を進めます。
方向を定める最も基本的な方法は「方位」であり、コンパスを使って進行方向を確認し、
距離は歩数で測る(歩測)かもしれません。
市街地では道路や歩道に沿って進むことが前提となるため、
縁石や塀、路側線など近くにある構造物を視覚的な手がかりにして方向を定め、速度を落として歩くことになります。
視界が開けているときに頼っていた遠方のランドマークは使えなくなり、
代わって触覚的なランドマークが重要となります。
こうした視覚的情報が得られない状況での移動行動は、晴眼者も視覚障害者の歩行と多くの点で共通しています。
未知の場所に関する情報の入手
目的地が未知の場合、人は通常「行ったことのある人に聞く」「地図を見る」などの方法で
情報を得るのが一般的です。
たとえば、世界地図やガイドブックを見たり、登山前に地形図でルートを検討したりするのがその例です。
かつては紙の地図が主流で、ドライバーには道路地図、営業職には都市地図が必携でした。
現在ではデジタル地図が普及し、スマートフォンで縮尺や情報を自在に切り替えながら移動するのが一般的です。
ナビゲーションアプリでは、目的地までのルートを自動で提示し、
「ターン・バイ・ターン(turn-by-turn)」方式によって、交差点や分岐で進行方向を音声や画面で案内してくれます。
この方式によって、利用者は地図全体を把握する必要がなく、
一つ一つの案内にしたがって進むだけで目的地に到達することができます。
しかし、こうした情報の多くは視覚的な提示を前提としているため、
視覚障害者にとっては利用が難しいという課題があります。
情報も地図もない時の移動
周囲に案内してくれる人がいなくて地図も存在しないとき、
人はどのようにして目的地を探すのでしょうか。
大航海時代の航海者や未踏峰に挑んだ登山者たちの行動は、こうした「情報なき移動」の好例です。
現代でも、新しく開通した道がどこに通じているかを確かめる場面では、同様の探査的行動が求められます。
視覚障害者にとって、こうした「情報のない状態」は日常的に発生しています。
さらに、視覚障害者にとって歩道の有無や交差点の形状、縁石の位置といった通常の地図に含まれない
いわゆる「近接環境」の情報も必要になります。
これらは現地での調査を通じて、触覚や聴覚を用いて得るしかありません。
無計画に探索を進めれば、自身の位置が分からなくなり、出発点に戻れなくなる可能性もあります。
そのため、歩いた経路を記憶・記録し、出発点へ戻る工夫が必要です。
「無意識」の行動と「意識」的な行動
街を歩く時、晴眼者も「線を辿る」「ランドマークを認識する」「距離や方向を記憶する」といった操作を
無意識のうちに行なっています。
しかし、視覚的手がかりを通じて空間を直感的に把握し、自動化している点が視覚障害者とは異なります。
視覚障害者はこれらをすべて意識的に行う必要があり、
方向の手がかりを探し、障害物を検知・回避しながら進まなければなりません。
歩道の端には電柱、駐輪自転車、商品陳列台などの障害物が多く、
端を辿って移動することが困難になる場面も少なくありません。
その結果、車道や空き地に誤って入り込むリスクが高まります。
不慣れな道を歩くことは単なる「移動」ではなく、多層的な認知的・身体的負荷を伴う複雑な課題となっています。
今後は、視覚障害者の街歩きにとって重要な近接環境の情報にも対応した実用的で高精度な支援技術の開発と、
誰もが安全に移動できる環境整備が一層求められます。