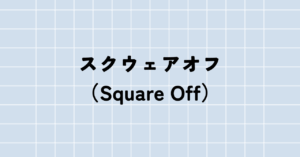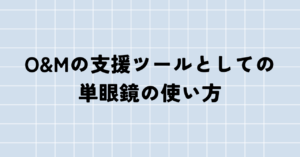はじめに
筆者は、ある自治体において10年間にわたりOM指導を受託してきました。
その指導内容の約半分は、経路学習と経路・場所の見分でした。
経路学習の対象は、通勤・通学路や生活関連経路(買い物、通院、ゴミ捨てなど)が多く、
経路学習が求められる背景には、勤務先の変更、工事による通行止め、新規店舗の利用、
あるいは視力低下により信号が確認できなくなり音響信号機のある経路へ変更せざるを得ない場合など
多様な要因が存在しました。
経路学習(route learning)とは
Golledge(1999)は、経路学習(route learning)について次のように述べています。
「経路学習とは、出発点と目的地を認識し、経路を構成する区間、曲がり角の角度、そしてそれらの順序を把握することを含んでいる。重要なのは、経路を辿るために必要な一連の行動を学習することである。環境の特徴、例えばランドマークは、角を曲がるきっかけや区間の距離を想起させる場合に限定して学習される。経路学習においては、道順や角の位置など経路上にある情報が優先され、経路から外れた情報は補助的なものとみなされる。」
この視点は、視覚障害者の経路学習にもそのまま適用できると考えられます。
1.経路学習の構成要素
経路学習には、以下の要素が含まれます。
- 起点と終点の識別
- ランドマークの選択・設定
- 道順記憶
- 行動手続きの記憶
- 近接環境の見分
これらの学習が成立するためには、基礎的な移動能力(進む・止まる、上る・下る、回転する、曲がるなど)と、
近接環境におけるナビゲーション能力(境界に沿った歩行、障害物検知・回避、進路方向の定位など)が
事前に習得されている必要があります。
したがって、新しい経路に先立ち、学習者が日常的に利用している経路を実際に歩行する様子を観察することは、
その能力を把握するうえで極めて有効です。
観察の焦点は安全性に置き、物との衝突、つまずき、転落、経路からの逸脱といった事象の有無を指標とします。
2.起点と終点の識別
市街地の目的地は大きく、街区の角にある場合と街区の辺にある場合に分けられます。
角にある場合は、交差点の認識により目的地の特定が比較的容易です。
一方、街区の辺に位置する場合は、目的地の外観やサインを直接認識する方法が考えられますが、
視覚障害がある人にはそれらの確認が困難なため、代替となるランドマークの設定が必要となります。
「角から何軒目」といった手がかりは現場では誤りが生じやすいものです。
さらに、図書館や市役所のように敷地内部に目的地がある場合、
敷地入口から建物入口までの案内表示は認識困難であることが多く、
この場合は敷地入口と建物入口を起点・終点とした経路の学習が必要です。
3.ランドマークの選択・設定
市街地では、交差点や曲がり角が経路を区切る自然なポイントですが、
私道を公道と誤認し、その結果交差点の数を誤って数えることがしばしば生じます。
そのため、道を確かめるための追加の目印としてランドマークを使うことが望ましいです。
ランドマークは、可能な限り動線上で確認できるものを選定します。
確認のために動線を外れる必要があるランドマークは、効率性と安全性の両面から適切ではありません。
際立つ対象が乏しい場合には、「電柱—ポスト—ベンチ」のように
連続する対象物を一組のランドマークとして利用する工夫も有効です。
4.道順記憶と行動手続きの記憶
経路を構成する区間と曲がり角の順序を記憶することを「道順記憶」と呼びます。
これに対し、道順に沿って実行する具体的行動を記憶することを「行動手続きの記憶」と呼びます。
行動手続きには、建物沿いの歩行、ランドマーク確認、道路横断などのナビゲーション行動に加え、
障害物や路面凹凸の検知・回避が含まれます。
白杖使用者は杖の操作、ロービジョンの人はランドマークや信号機を見つけるためのスキャニング等も該当します。
また、全盲の人とロービジョンの人、さらにロービジョンの人の保有視機能の程度により、とるべき行動は異なります。
この行動手続きの記憶は、反復により定着し、必要な反復回数は学習者の能力、経路の長さ、複雑さ、
困難さに応じて異なります。
5.近接環境の見分
経路学習を支える基盤として、路面の凹凸や勾配、歩道の有無や境界の形状、
ランドマークに適した経路上の特徴などを実地踏査で確認する「近接環境の見分」が不可欠です。
その際、環境内の危険箇所(例:深い段差、検知困難な構造物)や、
将来的に想定される危険(例:植栽や街路樹の成長、季節や気象条件による変化)についても
実地に検討することが重要です。
6.一人で歩くのか、それとも同行者と歩くのか
経路学習は、起点・終点の識別、ランドマークの設定、道順記憶、行動手続きの記憶、
近接環境の見分の相互作用により成立し、これらを適切に組み合わせることで安全な単独移動が可能となります。
他方で、視覚障害のある人が特定の経路を一人で歩くか、同行者と歩くかの判断には、
以下の要因が影響するとされています(Hersh, 2020)。
- 経路への慣れの度合い
- 不慣れな経路での移動が「一度きり」か「繰り返し」か
- 一度きりの不慣れな経路における同行者の有無
- O&M指導員や、適切なランドマークを示す支援者の有無
- 自信、必要性、目的地に行きたいという意欲等の個人的要因
おわりに
経路学習は、単に道順を覚える作業ではなく、前述の複数の要素の組み合わせによって成立します。
その過程では、学習者の保有視機能や経験、自信、意欲といった個人的要因に加え、
支援者の存在や環境条件も重要な役割を果たします。
実践の場では、反復練習を通じた行動手続きの定着や、安全性を確保するための近接環境の検討といった
基本的な要素に加え、本人の生活上の必要性や心理的要因を踏まえた支援が求められます。
また、一人で歩くか、同行者と歩くかの選択は、本人の自立性と安全性をめぐる重要な意思決定であり、
その判断は多様な要因に左右されます。
参考文献
Golledge, R.G. (1999). Human Wayfinding and Cognitive Maps. In R.G. Golledge (Ed.), Wayfinding Behavior: Cognitive Mapping and Other Spatial Processes. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press.
Hersh, M. (2020). Route learning by blind and partially sighted people, Journal of Blindness Innovation and Research, Vol. 10, No.2.

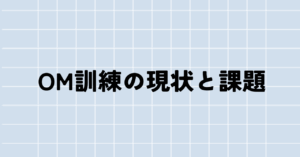
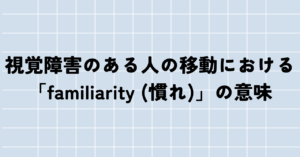
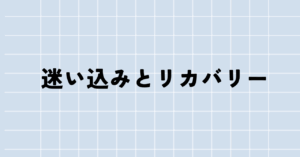
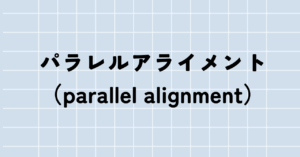
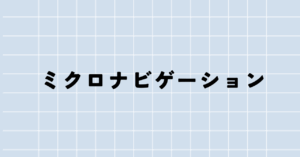
の使用場面と有効性-300x157.png)