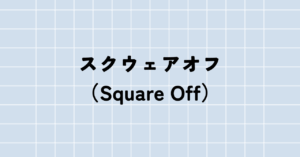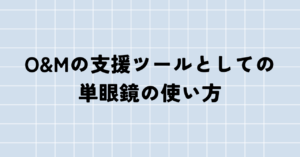1. OM訓練を担う人材と制度的背景
OM訓練を担う人材
日本では、OM(Orientation and Mobility、以下OM)訓練の提供に特別な資格は必要とされておらず、
制度上、誰でも実施可能である。
しかし現実には、その多くが「歩行訓練士」によって担われている。
歩行訓練士以外にも、作業療法士や理学療法士などがOM訓練を実施する例もある。
「歩行訓練士」が担っている役割
「歩行訓練士」は名称の印象とは異なり、歩行技術の指導にとどまらず、
点字やパソコン操作などのコミュニケーション訓練や生活技能訓練、福祉情報の提供まで幅広く対応する、
いわば視覚障害福祉における「何でも屋」といえる役割を担っている(文献1)。
そのため、「歩行訓練」という言葉が、文脈によってOM訓練のみを指す場合と、
OMを含む多領域の訓練・相談業務全体を指す場合とが混在し、
OM訓練固有の課題が他の訓練の議論に埋もれてしまう傾向がある。
不足が議論されている「歩行訓練士」とは?
2024年現在、実働している歩行訓練士は246名であるが(文献2)、
この数が多いのか少ないのかを判断する明確な根拠はほとんどない。
歩行訓練士不足が議論される際も、それが「何でも屋」としての業務全体に対する人員不足を指すのか、
OM訓練を提供する人材の不足を指すのかが曖昧なままである。
2. 歴史的経緯と対象者の変遷
視覚障害リハビリテーションプログラムの変遷
第1回歩行訓練士養成講習会から半世紀以上経過した(文献3)。
1960年ごろまでの視覚障害リハビリテーションは、国立施設を中心とした三療師養成プログラムが主流であった。
1966年には日本ライトハウス職業生活訓練センターが開設されたのを契機に、
1970〜80年代には自立生活訓練プログラムを提供する施設が相次いで開設され、隆盛期を迎えた。
このプログラムは、それ以前からあった職業訓練プログラム(三療師の養成による職業的自立)に
先立つ段階(pre-vocational training)として位置づけられ、
養成施設での学習や寮生活に必要な技能習得を目的としていた。
OMはその主要訓練項目の一つであった。
OM訓練の対象者層
当時の入所生は現在より若年で身体的に活動的な視覚障害者が多く、
OM訓練も均質な対象者層に合わせた画一的な内容であった。
そのため、もともと米国で若年の失明軍人を対象として開発されたプログラム(文献4)との親和性が高かった。
一方、弱視者向けの訓練プログラムは十分に開発されておらず、
「目隠し訓練」のように全盲者として扱うのが一般的であった。
また、高齢者や重複障害者に対しては、既存のプログラムを改変する必要があったが、
当時はその体制が整わず、就労の可能性が低いと見なされたこともあり、OM訓練の対象外とされることが多かった。
3. OM訓練の伝統的構成
伝統的なOM訓練
伝統的なOM訓練では以下の順に指導を行う。
1.ガイドと歩く方法
2. 手・腕を使った防御法
3.平行・垂直方向の確保法
4.杖の操作法
まず屋内の管理された環境で技能を習得させ、その後、住宅地や商業地など複雑な屋外環境、
さらに公共交通機関の利用へと段階的に移行する(文献5)。
OM指導の基本原則
OM指導の基本原則の一つは、必要となる前にすべての前提技能・技術を論理的順序で導入しておくことである(文献6)。
施設入所者への訓練では、施設および周辺地域を利用して訓練が行われた。
訓練地は難易度別にあらかじめ設定され、進捗に応じて訓練地を変更しながら行われた。
形式としては、あらかじめ作成された画一的プログラムに沿って指導者が学習内容・方法を具体的に提示し、
学習者がそれに従う形が主流であり、現在多く見られる発見学習(discovery learning)の手法は一般的ではなかった。
職業訓練の前段階として行われたため、終了後は同じ施設で職業訓練期間を過ごすことになる。
しかし、職業訓練を終えて社会に戻る段階で、本当の移動課題が明らかになったり、
あるいは職業訓練中に視覚障害が重度化したりといった理由で、
再度のOM訓練が必要となる例も少なくなかった。
4. 現状の課題
技能習得に偏るOM訓練
今日でも、白杖を用いた歩行法や特定ルートの習得はOM訓練の中心的テーマであるが、
技能習得に偏重する傾向が強く、OMの本質や方法論を見直す機会が限られている。
歩行訓練士養成課程で教えられる技術の多くは50年以上前の手法が中心であり、
その有効性は当時と似た特性を持つ利用者層に限定される可能性がある。
OM訓練の指導法の変遷
近年の指導書では、「ガイドと歩く方法」や「手と腕を使った防御法」が初期段階に位置づけられているからといって、
それらが「杖の操作法」の前提条件であるべきではないとされている。
むしろ、杖の使用が有益な学習者には、できる限り早期に導入することが推奨されている(文献7)。
また、高齢視覚障害者向けに、伝統的技術を身体特性に合わせて調整した手法を提案する動きも見られる(文献8)。
しかし、古典的技術を中心に学んだ新人訓練士は、多様化・複雑化する現場ニーズに直面した際、
十分に対応できないリスクがある。
特に、新たな実践モデルや適応策の有効性・安全性を裏付ける実証的証拠が乏しいため、
自信や実践知の蓄積が難しい状況にある。
OM訓練の本来の目的を果たす人材を育成するために
OM訓練の本来の目的は、利用者が直面する即時的かつ現実的な環境課題に対応できる力を育むことである。
OMには、物との衝突、転倒、方向喪失といった危険や、交差点などでの車両交通との交差といったリスクが伴うため、
それらを安全に回避できるようにすることが訓練の核心である。
OM訓練は利用者の心理的・身体的能力(残存視力も含む)、
移動環境、意欲などに応じて構成されるべき高度に個別的なプログラムであり、
訓練士は多様な技術・用具の中から最適なものを選択し、利用者の生活に即した支援を提供する必要がある。
さらに、指導者には、視覚障害者の移動特性や移動の容易性に関する十分な知識を持ち、
訓練生の主体性を尊重した指導ができる資質が求められる。
このような人材をどのように養成するかについては、既存の「歩行訓練士」養成プログラムの枠にとらわれず、
広く議論を重ね、当事者の安全な移動に寄与する体制を構築していく必要がある。
参考文献
1. 日本盲人会連合 (2017). 視覚障害者のニーズに対応した機能訓練事業所の効果的・効率的な運営の在り方に関する調査研究事業報告書、日本盲人会連合.
2. 視覚障害者の生活訓練実施機関の現状 (2024)
https://www.lighthouse.or.jp/rehab/wp-content/uploads/2024/08/2024syu-ryo.pdf
3. 木塚泰弘(2013). 歩行訓練研修会から視覚障害生活訓練等指導者養成課程までの42年間のあゆみ、視覚障害リハビリテーション、第78号
4.Hill, E. & Ponder, P. (1976). Orientation and Mobility Techniques, American Foundation for the Blind, New York, NY.
5.LaGrow, S. & Weessies, M. (1994). Orientation and Mobility: Techniques for Independence, The Dunmore Press Ltd., Palmerston North, New Zealand.
6.LaGrow, S. & Long, R. (2011). Orientation and Mobility: Techniques for Independence, 2nd edition, revised and expanded, Association for Education and Rehabilitation of the Blind and Visually impaired.
7.Fazzi, D.L. & Barlow, J.M. (2017). Orientation and Mobility Techniques, a Guide for the Practitioner, 2nd edition, AFB Press.
8.Page, A. & Bozeman, L. (2016). Modifying Orientation and Mobility Technique for Older Adults with Visual Impairments, In N. Griffin-Shirley and L. Bozeman (Ed.) O&M for independent living, Strategies for teaching orientation and mobility to older adults, AFB Press.

-300x157.png)
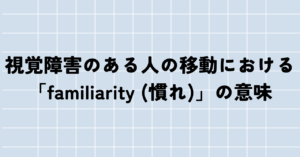
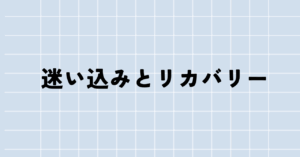
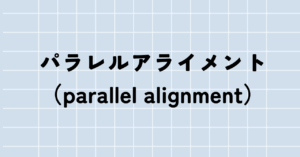
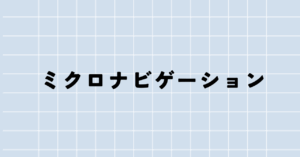
の使用場面と有効性-300x157.png)